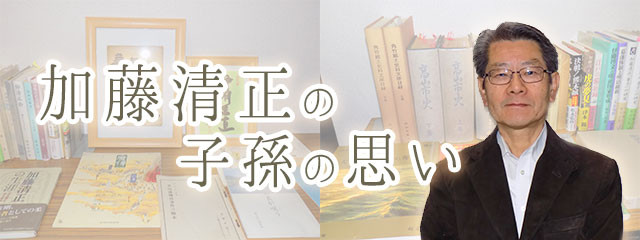紀貫之 古今九四 春下
21.三輪山をしかもかくすか春霞人にしられぬ花やさくらん
(みわやまを しかもかくすか はるがすみ ひとにしられぬ はなやさくらん)
(私訳)三輪山をそんなに隠すか春霞。その春霞の中に人には知られぬ美しい花がきっとたわわに咲いているのであろう。
元斎解説
正吉の申されたのは三輪の山には形を隠すものがあるという古事があるという。それを思い出して読んだ。しかも、かくすは「それほどまでに隠す」という意味である。花ですら人に知られまいとし、花の盛りが霞の中に鳴り響いている。
この古事をよく考え抜いてみた。昔大和の国に女がいた。夜な夜な男が通っていたにもかかわらず、ついに姿を見せることはなかった。「姿を見せよ」と男が頻りに言えば「汝の櫛が箪笥にあるはず」という。見れば朽(くち)縄(なわめ)(蛇)であった。男は驚いて逃げて行った。
その夜男が来て我が姿を見て「すぐに私を憎むようになるだろう」と思って虚しく別れてしまった。女は恐ろしい姿をしていたが、別れとなればやはり悲しく思って、針に糸をつけて、男の狩衣の後ろに差しつけて糸の行方を求めていくと、三輪(みわ)の明神の祠の中に留まる糸の残り三(み)分(わ)けがあったので、三輪の明神と名付けなさったという事である。
訳者注記
正吉とは、元斎の祖父木戸範実。範実公は母から冷泉流を継承し、東常和(とうのつねかず)から二条流を学んだと言われる。元斎の父は羽生城の城主だった木戸忠朝公であるが、元斎が父から和歌を習ったという話は寡聞にして聞かない。
素性法し 古今九五 春下
22.いさけふは春の山辺にましりなん暮なはなけの花のかけかは
(いざきょうは はるのやまべに まじりなん くれなばなげの はなのかげかわ)
(私訳)さあ今日は、春の山辺に遊びに行こう。日が暮れたらなくなりそうな花陰ではないよ。
元斎解説
「いさ」とはさそう心地である。引率の言葉である。「くれなばなけ」は、なくなる花ではない、だから終日見ようという事である。「け」文字は清音である。この哥を捉えて、定家卿自らも、どこかは分からないが、日が暮れると、それくらいでなくならない花を頼みにして、月を見たという事だ。
訳者注記
此処には書いていないが、花は桜であろう。春の山辺に分け入り、明るく咲くおびただしい数の桜を見に行ったのであろう。日が暮れても花陰は明るく、桜の木の下で野宿すらできたのかもしれない。
実際に定家卿はこの歌を実践したとのこと。月の光を浴びた桜の下に憩う心地よさを満喫したに違いない。
同 古今一〇九 春下
23.木つたへはをのか羽風に散花を誰に負せてここら鳴らん
(こつたえば おのがはかぜに ちるはなを だれにおおせて ここらなくらん)
(私訳)木の枝を忙しく伝う鶯の、自らの羽風に散る桜の花を、一体誰のせいだと思って、恨めし気にそんなに盛んに鳴くのだろうか。
元斎解説
鶯はひとところに、しばしもいないものである。自分の羽の風で散っているのに誰がこんなことをするのだとでも言うように、恨み顔で鳴いているのである。「ここら」は鳴く声が多いという事、「集」の字を用いる人におられる。
訳者注記
鶯の小刻みなせわし気な動きが想像でき面白い哥であろう。自然は人間ほど器用ではなく、又(当時の)人間ほど自然を気遣っていないかもしれない、という事を思ってしまうユーモラスな哥だ。
「ここら」は、数や量について、たくさん、また、程度について、たいへんという意味。(旺文社古語辞典)
権中納言定家 拾遺愚草八四二 六百番歌合冬「残菊」
24.白菊のちらぬは残る色かほに春は風をも恨ぬる哉
(しらぎくの ちらぬはのこる いろかおに はるはかぜをも うらみぬるかな)
(私訳)白菊の散らないまでも褪せた色や姿をみて、それを春風のせいにして恨んだものだな。
元斎解説
菊は風にも散らぬものである。しかし、散らない菊もいつまでも咲いているわけではないことを知りながら、春の花には風を恨むのである。省みるべきものである。花といわないで、上句より続けているが、意味がよくわかる。上級者の仕業である。
(引用の漢文四行を省略。)
訳者注記
桜の花は春風によって潔く散り、後に何も残さないが、菊の花は春風では散らない。その代わり醜くしおれてしまう。已むことを得ずそれを春風のせいにするのである。人とは何事も、何かのせいにして安心を得るほかあるまいということか。
この稿続く。
令和5年1月2日