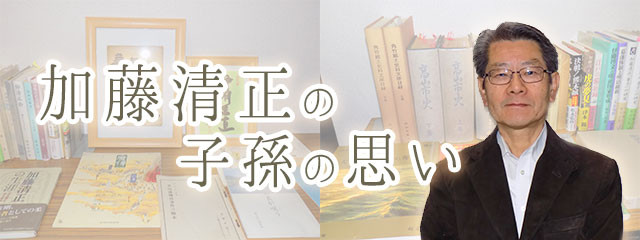読人しらす 古今一四九
31.声はして泪は見えぬ時鳥我衣手のひつをからなん
(こえはして なみだはみえぬ ほととぎす わがころもでの ひつをからなん)
(私訳)悲しげになく声はすれども、涙は見えない時鳥よ。悲しみで濡れそぼった我が袖を借りて心ゆくまで鳴くがいい。
元斎解説
郭公がしきりに鳴くのは自分の心の思いを知らせたいと思ってであろうか。しかしながら涙が見えないので、私の濡れた袖を借りてくれ、貸してあげるのに、という心である。「なん」はどの哥でも「なになにしてください」の意と心得るべきである。
訳者注記
時鳥と作者の二つの悲しみが同時に進行していて、作者の袖は悲しみの涙で濡れているのに、時鳥の目に涙がないのを見て、「我衣手のひつ」を借りてくれ。といっているのである。「ひつ」は「泌」、液体がしみ出ること、と辞書にある。
悲しみは同じであるから、涙も分け合いたいという事であろうか。
紀友則 古今一五三
32.五月雨に物おもひをれは杜鵑夜ふかく鳴ていつち行らん
(さみだれに ものおもいおれば ほととぎす よふかくなきて いずちゆくらん)
(私訳)五月雨のように乱れ心で思い乱れていると、夜に鳴かない鳥がこの夜更けに、杜鵑よ、私と同じく思い乱れているせいなのか、鳴きながらどこへ行くというのだ。
元斎解説
五月雨が降る日に物思いをしているのではない。五月雨のように乱れ心でもの思いしているのである。単に乱れてでは足りないという事である。夜に鳴く鳥はいないものだが、このほととぎすが夜更けに鳴くのは、私のように乱れて物を思っているからだろうかと。
訳者注記
元斎の解釈は独特で見事だ。一般的な解釈と思われるので、新潮日本古典集成から引用する。
(新潮訳)梅雨のうっとうしいこのごろ、もの思いに沈んでいると、その夜更け、時鳥が、悲しい声でないて飛ぶ。いったいどこへ行くのだろう。
(新潮解説)『古今集』の中でも名品とされる歌。梅雨の夜の静寂と、それを破る時鳥の鋭い声。それが闇の中に尾を引いて消えると、闇は一層濃く、静寂はさらに深まる。
この稿続く。
令和5年1月10日